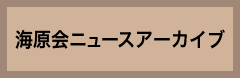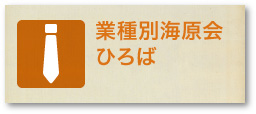同期会・同窓会ひろば
同期会・同窓会ひろば
平成14年卒 第13回学年同窓会
1月20日(土)に毎年恒例の学年同窓会を母校カフェテリアで開催しました。今年は那須高原海城での勤務を終えられた茂木先生に久々にお越しいただきました。また、福島先生からは昨今の教育現場の変化についてお話を伺いました。同窓生の出席者も例年と比べて多く、皆さんからの近況報告は非常に興味深いものでした。話をする中で、実は同じ仕事に関わっていることが分かったり、今後の協業に繋がりそうな話が出たりと、第一線で活躍される皆さんが集まると、思わぬ収穫がありますね。
学年同窓会は、今後も毎年1月に開催予定です。在学時にはあまり話したことがなかった人とも意外と話が弾むものなので、是非ご参加ください!
案内の葉書きやメールが届いていない方は、kaijo2002@googlegroups.comまでご連絡ください。また、Facebookに「海城2002年卒」というグループがありますので、是非ご参加ください。
(矢野祐規 記)
昭和41年中学卒 同窓会
★来年は高校卒業50周年の企画募集中★
3月17日、今年も20名が新宿文化センターに集まりました。初登場は、いまだ現役で変わらぬダンディ男の池田健一君、福祉事業で頑張る生真面目な須永正君、ホンダを引退した市瀬一寛君の3名。市瀬君はホンダ時代にアコード、プレリュード、NSXなどのエクステリアデザイナーとして大活躍。羽田昶先生はまもなく79歳ですが、お元気に能・狂言・歌舞伎などの講座を持たれる現役です。来年は高校卒業50周年。企画を募集中。
=======まで連絡下さい。 (千賀孝雄)
★会報には千賀さんのアドレスを載せます。今回、HPをご覧になったからは当HPの「海原会へのお問い合わせ・ご連絡」よりご連絡ください。
昭和62年卒同期会
3月18日(日)に昭和62年卒の同期会を開催しました。
1次会を海城学園カフェテリア、2次会を駅前の鳥良で開催。昨年の卒業30周年では大掛かりに催したので、今年はメリハリをつけて質実剛健な会としました。
1次会には6組担任の中村先生が顔を出してくださいました。私たちにとって最若手という印象だった中村先生もすっかり重鎮に。思えば10クラスあった私たちの学年で担任をしていただいた先生で今も在職されているのは中村先生だけになってしまいました。
質実剛健過ぎて1次会の酒があっという間に無くなってしまい、早々に2次会の会場へ。2次会からの参加者は既に盛り上がっている状況を見て集合時間を間違えたかと驚くほど。
1次会~・2次会~の参加者を合わせて32名が集まりました。
奇しくも当日は海城の卒業式。31学年下が巣立つ日に我々は参集したことになります。時は過ぎて、来年度はとうとうみんな50才。でも、来年も同期会やります!
画像上:一次会メンバー
画像中:中村先生の緊急講義
画像下:当日は卒業式だった
平成2年卒・6年10組茂木組 クラス会
去る2月18日(土)、蓮見昌幸くん幹事のもと、担任の茂木先生をお招きして平成時代最後のクラス会を開催しました。
ちょうど30年前、高校2年の冬休み明けの時期に時代が昭和から平成へと変わりました。
あの当時の賑やかさをそのままに、楽しいクラス会を過ごすことができました。
このクラス会で取り決めている「茂木先生による次回幹事のご指名制度」。
この制度もすっかり根付き、毎回、スリリングな締めの場になっています。
そんな次回のクラス会の幹事は、柏崎くんに決まりました。
次回は2020年に開催。
多くのクラスメイトをお誘いできるよう、来年から各方面に連絡を回してみるとのこのでした。
それでは2年後、また 先生も生徒たちも、元気な姿でお会いしましょう!
写真①:集合写真
写真②:次回幹事予定の柏崎くん(左)と、今回幹事の蓮見くん(右)
【平成11年卒】『応仁の乱』の著者、新たな本を出版
私の友人である呉座勇一君(平成11年卒)が、このたび新たな本を出版しました。『陰謀の日本中世史』(角川新書、880円+税)です。
呉座君は、2016年に『応仁の乱-戦国時代を生んだ大乱』(中公新書、900円+税)を出版、同書は47万部突破の大ベストセラーとなりました。呉座君自身も、「歴史秘話ヒストリア」(NHK)、「世界一受けたい授業」(日本テレビ系)、ゴロウ・デラックス(TBS系)などのテレビや雑誌に多数出演、今や日本中世史のホープとも言うべき存在となっております。
本書では、前作でも取り上げた応仁の乱に加え、保元・平治の乱、平氏一門と反平氏勢力との抗争、本能寺の変、関ヶ原の戦いなどについて取り上げ、世間に知られている通説について、証拠を示しつつ疑問を呈しております。それは論理的に展開されており、まさに論理的思考力を身に着けることができます。
また、陰謀論の特徴やパターンを太字で強調していることも、世間に流布している言説が陰謀か否かを見極める上での一助になると思います。
なお、陰謀論とは直接関係ありませんが、個人的には、「勝負というものは、双方が多くの過ちを犯し、より過ちが少ない方が勝利する」の一節が、あらゆる勝負に臨む上で参考になる言葉であると感じました。完璧に準備して臨んでも、実際には思いもよらないミスをすることが少なくない。そんな時にいかにダメージ(肉体的、精神的双方)を抑えられるか、ダメージコントロールの重要性を語っていると思います。
同窓生の皆様、本書に興味を持たれた方は、ぜひ書店に行かれて、本書をお買い上げいただきますと幸いです。
リニューアル以前の記事は旧 広場で見られます。